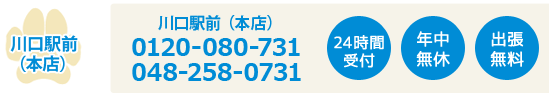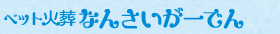愛猫の「老衰」と向き合う時間は、飼い主様にとって、覚悟はしていても、やはりつらく、そして様々な感情が交差する、非常にデリケートな時間です。
この記事では、そんな飼い主様の心に優しく寄り添いながら、猫の老衰とはどのようなものなのか、その具体的なサインや症状、そして、愛猫が、その命の灯火を閉じるその日まで、安らかで、尊厳ある日々を送るために、ご家族ができる具体的な備えと対処法について、一つひとつ丁寧に解説していきます。

↑お問い合わせはこちらのバナーをクリック↑
猫の寿命は?
愛猫の「老い」を考える上で、まず、猫の平均寿命や、人間との年齢の比較を知っておくことは、ご自身の愛猫が、今、どのようなライフステージにいるのかを理解するための、一つの目安となります。
猫の年齢と人間の年齢の比較
猫の時間は、人間の時間よりも、ずっと早く流れていきます。一般的に、猫は最初の1年で、人間でいうところの17歳~18歳くらいまで成長し、2年で24歳程度の成猫になります。
その後は、1年ごとに、およそ4歳ずつ年を重ねていく、と計算されます。
例えば、10歳の猫であれば、人間では56歳くらい。15歳にもなれば、76歳の、立派な高齢者です。
この年齢換算を知っておくと、愛猫の行動の変化を、「もう、そんなお年頃なんだな」と、より深く理解し、受け入れることができるようになります。
猫の平均寿命
近年の獣医療の進歩や、キャットフードの品質向上、そして完全室内飼育の普及により、猫の平均寿命は、著しく延びています。
一般社団法人ペットフード協会が発表した「2023年(令和5年)全国犬猫飼育実態調査」によると、猫全体の平均寿命は15.79歳でした。
特に、「家の外に出ない」完全室内飼育の猫の平均寿命は16.22歳であるのに対し、「家の外に出る」猫の平均寿命は14.24歳と、その差は明らかです。
交通事故や、他の猫との喧嘩による感染症といった、屋外のリスクを避けることが、長寿の大きな要因となっていることが分かります。
猫の種類や性別による寿命の差
犬ほど顕著ではありませんが、猫の種類(猫種)によっても、平均寿命には、やや差が見られます。
一般的に、日本猫などのミックス(雑種)は、特定の遺伝性疾患が少ないため、長生きする傾向にあるといわれています。
また、性別については、去勢・避妊手術の有無が、寿命に大きく影響します。生殖器系の病気のリスクを低減できることや、発情期のストレス、あるいは縄張り争いによる喧嘩などを避けられるため、手術を受けた猫の方が、長生きする傾向にある、とされています。
猫が老衰に近づいてきたときに見せる症状

愛猫が、シニア期から、さらにその先の「終末期」へと近づいてくると、その心と体には、いくつかの特徴的なサインが現れるようになります。
それは、命が、次のステージへと向かうための、自然な準備の始まりです。
睡眠時間の増加
まず、最も分かりやすい変化が、睡眠時間です。
元々、猫はよく眠る動物ですが、老衰が進むと、一日のほとんど、時には20時間以上を、眠って、あるいは、うとうとと微睡んで過ごすようになります。
基礎体力が低下し、活動による疲労を回復するために、より多くの休息が必要になるためです。呼びかけにも、あまり反応せず、静かに丸まっている時間が増えてきたら、それは老化のサインの一つと捉えましょう。
動く時間の減少
睡眠時間が増えるのと反比例して、活動する時間は、著しく減少します。
大好きだったおもちゃにも、あまり興味を示さなくなり、キャットタワーに駆け上ることも、少なくなってきます。
これは、筋力の低下や、関節の痛みなどによって、活発に動くこと自体が、億劫になってくるためです。
無理に遊ばせようとせず、愛猫のペースに合わせて、静かに過ごせる環境を整えてあげることが大切です。
毛並みや毛艶の悪化
健康のバロメーターともいえる、毛並みにも変化が現れます。猫は、本来、非常にきれい好きな動物で、一日の多くの時間を、毛づくろい(グルーミング)に費やします。
しかし、老いてくると、体力の低下や、体の柔軟性が失われることで、このグルーミングを、あまりしなくなります。
その結果、毛にツヤがなくなり、パサついたり、毛玉ができやすくなったりします。
また、腎臓などの内臓機能の低下も、毛並みの悪化として現れることがあります。
食欲の低下
大好きだったご飯を、残すようになったり、全く食べなくなったりするのも、老衰の顕著なサインです。
これは、消化機能や、代謝機能の低下に加え、嗅覚が衰えて、食べ物の匂いを感じにくくなることも、原因の一つとされています。
ただし、急激な食欲不振は、腎臓病や、口内炎といった、治療可能な病気が隠れている可能性もあります。
「年のせいだ」と決めつけず、一度、動物病院で診てもらうことも重要です。
トイレミスと夜鳴きの増加
これまで、一度も失敗したことがなかったのに、トイレ以外の場所で、粗相をしてしまうことが増えてきます。
これは、足腰が弱り、トイレまで間に合わなかったり、トイレの縁をまたぐのが、辛くなったりすることが原因です。
また、特に夜中に、目的もなく、大きな声で鳴き続ける「夜鳴き」が見られることもあります。
これは、人間でいうところの「認知症」に近い症状で、目や耳が不自由になることへの不安感や、昼夜の感覚が、不確かになることから起こると考えられています。
飼い主の呼びかけに対する反応の悪化
名前を呼んでも、振り向かない。おやつの袋を開ける音にも、気づかない。こうした、聴力の低下も、老化のサインです。
また、視力も徐々に衰え、暗い場所では、物にぶつかったり、段差を踏み外したりすることもあります。愛猫を驚かせないよう、視界に入ってから、優しく声をかけたり、体にそっと触れたりといった、コミュニケーションの工夫が必要になります。
巻き爪
若い頃は、爪とぎをすることで、常に爪の長さを、自分で調整していました。
しかし、高齢になると、活動量の低下から、爪とぎの回数が減り、爪が伸び放題になってしまうことがあります。
伸びすぎた爪は、肉球に食い込んでしまい、痛みや炎症の原因となります。
これが「巻き爪」です。歩き方が、どこかぎこちないと感じたら、一度、肉球をチェックしてあげる必要があります。
老衰してきた猫の症状に気づいたらすること
愛猫に、こうした老化のサインが見られ始めたとき、飼い主として、何をしてあげられるのでしょうか。
大切なのは、これまでの生活環境を見直し、愛猫が、少しでも快適に、そして安全に、日々を過ごせるように、整えてあげることです。
食事と水分補給の調整
食欲が落ちてきた愛猫には、食事の工夫が必要です。ドライフードが食べにくそうであれば、ぬるま湯でふやかして、柔らかくしてあげましょう。
また、匂いが強く、嗜好性の高いウェットフードに切り替えるのも、有効な方法です。
一度にたくさん食べられない場合は、食事の回数を、一日3回から4回に増やし、少量ずつ与えるようにします。
高齢の猫は、脱水症状を起こしやすいため、水分補給も非常に重要です。
ウェットフードは、食事と同時に水分も補給できるため、おすすめです。また、水飲み場を、家のあちこちに増やしてあげることで、水を飲む機会を、自然と増やすことができます。
段差や障害物を少なくする
筋力が低下した老猫にとって、家の中の、ほんの少しの段差も、大きな障害物となります。ソファやベッドへの上り下りが、辛そうであれば、横に小さなステップや、スロープを設置してあげましょう。
また、床に物を置かないように整理し、愛猫が、安全に移動できる動線を、確保してあげることも大切です。
キャットタワーも、一番上まで登れなくなることが多いため、低い段だけでも楽しめるように、配置を工夫してあげると良いでしょう。
滑らない床にする
足腰が弱ってくると、滑りやすいフローリングの床では、足を踏ん張ることができず、転倒しやすくなります。
怪我を防ぐために、愛猫がよく通る場所には、コルクマットや、カーペット、あるいは滑り止めのマットなどを敷いてあげましょう。
こうした、足元への配慮が、愛猫の行動範囲を狭めず、最後まで、自力で歩く意欲を、支えることに繋がります。
行動できる範囲を狭くする
認知機能が低下したり、目や耳が不自由になったりすると、広い家の中を歩き回ることが、かえって愛猫の不安を煽り、危険を伴う場合があります。
そのような場合は、あえて、リビングの一角など、飼い主様の目の届く範囲に、愛猫専用のスペースを作り、そこで安心して過ごせるように、行動範囲を制限してあげることも、有効なケアの一つです。
そのスペースの中に、ベッド、トイレ、食事場所を、コンパクトにまとめてあげると、移動の負担も軽減できます。
動物病院で診てもらう
愛猫の老化のサインに気づいたら、「もう年だから仕方ない」と自己判断せず、まずは一度、動物病院で、獣医師の診察を受けることを、強くお勧めします。
一見、老衰に見える症状が、実は、治療可能な「病気」のサインであることも、少なくありません。特に、老猫に多い、慢性腎臓病や、甲状腺機能亢進症、関節炎といった病気は、早期に発見し、適切な治療や、投薬を行うことで、その進行を遅らせ、苦痛を和らげることができます。
愛猫のQOL(生活の質)を、最後まで高く保つためにも、専門家である獣医師と、密に連携することが重要です。
老猫してきた猫の介護の方法
やがて、愛猫が自力で生活することが、困難になってきたとき。飼い主様による、愛情のこもった「介護」が、必要になります。
排泄の介助
自力でトイレに行けなくなったり、粗相が増えたりした場合は、ペット用のおむつを利用するのが、一つの方法です。ただし、おむつは、こまめに交換しないと、皮膚がかぶれたり、不衛生になったりするため、注意が必要です。
また、寝たきりの状態でも、トイレの近くまで、優しく抱いて連れて行ってあげると、自力で排泄してくれることもあります。
排泄後は、お尻の周りを、赤ちゃん用のおしりふきや、湿らせたコットンなどで、優しく拭き取り、常に清潔な状態を保ってあげましょう。
食事の介助
自力でご飯を食べられなくなった場合は、食事の介助が必要です。ウェットフードを、指やスプーンに乗せて、口元まで運んであげると、食べてくれることがあります。それでも食べない場合は、シリンジ(針のない注射器)を使い、流動食を、口の横から、少しずつ、ゆっくりと流し込んであげる方法もあります。この際、誤嚥(ごえん)して、気管に入ってしまわないよう、細心の注意が必要です。
寝たきりへの対応
寝たきりの状態になったら、最も注意すべきなのが「床ずれ(褥瘡)」です。
体の同じ場所に、長時間圧力がかかり続けることで、その部分の血行が悪くなり、皮膚が壊死してしまう、非常に痛みを伴う症状です。 これを防ぐためには、2~3時間おきに、体の向きを変えてあげる「体位変換」が、絶対に不可欠です。
また、体圧を分散させる、低反発のマットや、クッション、あるいは、ペット用の介護ベッドなどを活用するのも、非常に有効です。
猫が老衰する前に備えておきたいこと
愛猫が、穏やかで、幸せなシニアライフを送るためには、症状が現れてから対処するのではなく、元気なうちから、将来を見据えた「備え」をしておくことが、何よりも大切です。
老猫に適した飼育環境を整える
まだ元気なうちから、家の中の環境を、シニア猫仕様に、少しずつアップデートしていきましょう。
高いキャットタワーを、低い段差のものに買い替えたり、床に滑り止めのマットを敷いたり、トイレを、縁の低い、またぎやすいタイプのものに変えたり。
こうした、小さな配慮の積み重ねが、愛猫が、年を重ねても、安全に、そして尊厳を持って暮らし続けるための、大きな助けとなります。
猫の年齢に合わせた餌を与える
キャットフードには、子猫用、成猫用、そして高齢猫(シニア)用と、ライフステージに合わせた、様々な種類があります。7歳を過ぎたあたりから、徐々に、シニア用のフードへと切り替えていくのが良いでしょう。
シニア用のフードは、運動量が落ちた猫のために、カロリーが控えめに調整されていたり、衰えがちな腎臓の健康に配慮した成分が、配合されていたりします。
愛猫の年齢と、健康状態に合わせた、最適なフードを選ぶことが、健康寿命を延ばす鍵となります。
水をしっかり与える
高齢の猫は、喉の渇きを感じにくくなるため、飲水量が減りがちです。
水分不足は、脱水症状や、老猫に非常に多い、慢性腎臓病の悪化に直結します。いつでも、新鮮な水が飲めるように、水飲み場を、家の複数個所に設置してあげましょう。
また、流れる水を好む猫も多いため、噴水式の給水器を導入するのも、飲水量を増やす上で、非常に効果的です。
健康診断を定期的に受ける
猫は、不調を隠すのが、非常に上手な動物です。飼い主様が見て、明らかに様子がおかしいと感じたときには、すでに病気が、かなり進行してしまっているケースも少なくありません。
そのため、特に7歳を過ぎたシニア期に入ったら、何も症状がなくても、半年に一度は、動物病院で、定期的な健康診断を受けることを、強くお勧めします。
血液検査などを行うことで、様々な病気の早期発見に繋がり、結果として、愛猫の寿命を延ばし、QOL(生活の質)を、高く維持することができます。
少しでも違和感があったら医師に診てもらう
定期健診だけでなく、「いつもと、少しだけ様子が違う」という、飼い主様の「直感」は、非常に重要です。
「なんとなく、元気がない」「食欲が、少し落ちた気がする」「トイレの回数が増えた」といった、些細な変化が、大きな病気のサインであることもあります。
「年のせいかな?」と、自己判断せずに、少しでも気になることがあれば、ためらわずに、かかりつけの獣医師に相談する。
その習慣が、愛猫の命を救うことに繋がるかもしれません。
愛情を注ぎ猫の老いと向き合おう

今回は、大切な家族である愛猫の「老衰」について、そのサインから、飼い主様ができる具体的なケア、そして穏やかな最期を迎えるための、事前の備えまでを、詳しく解説しました。
大切なのは、その避けられないお別れの瞬間まで、後悔することなく、深い愛情を注ぎ続けることです。
これまでの、たくさんの幸せな思い出に、心からの「ありがとう」を伝え、そして、最期の瞬間まで、優しく、温かく、見守ってあげること。
それこそが、飼い主として、愛猫にしてあげられる、最大で、そして最高の贈り物ではないでしょうか。
なんさいがーでんの看板猫

そら
看板猫兼店長
なんさいがーでんの看板猫兼店長をしている「そら」。
店長を任され早3年、大切なペットとのお別れをしに来られた飼い主様の心の拠り所になっている。
-
千葉県 全域対応
<主な訪問対応エリア>
野田市|流山市|柏市|松戸市|市川市|鎌ヶ谷市|浦安市 -
群馬県 全域対応
<主な訪問対応エリア>
館林市|太田市|板倉町|昭和町|千代田町|大泉町|明和町|邑楽町|太田市 -
神奈川県 全域対応
<主な訪問対応エリア>
相模原市|川崎市|横浜市|愛甲郡|中郡|座間市|厚木市|綾瀬市|伊勢原市|海老名市|鎌倉市|秦野市|平塚市
藤沢市|大和市|高座郡寒川町 -